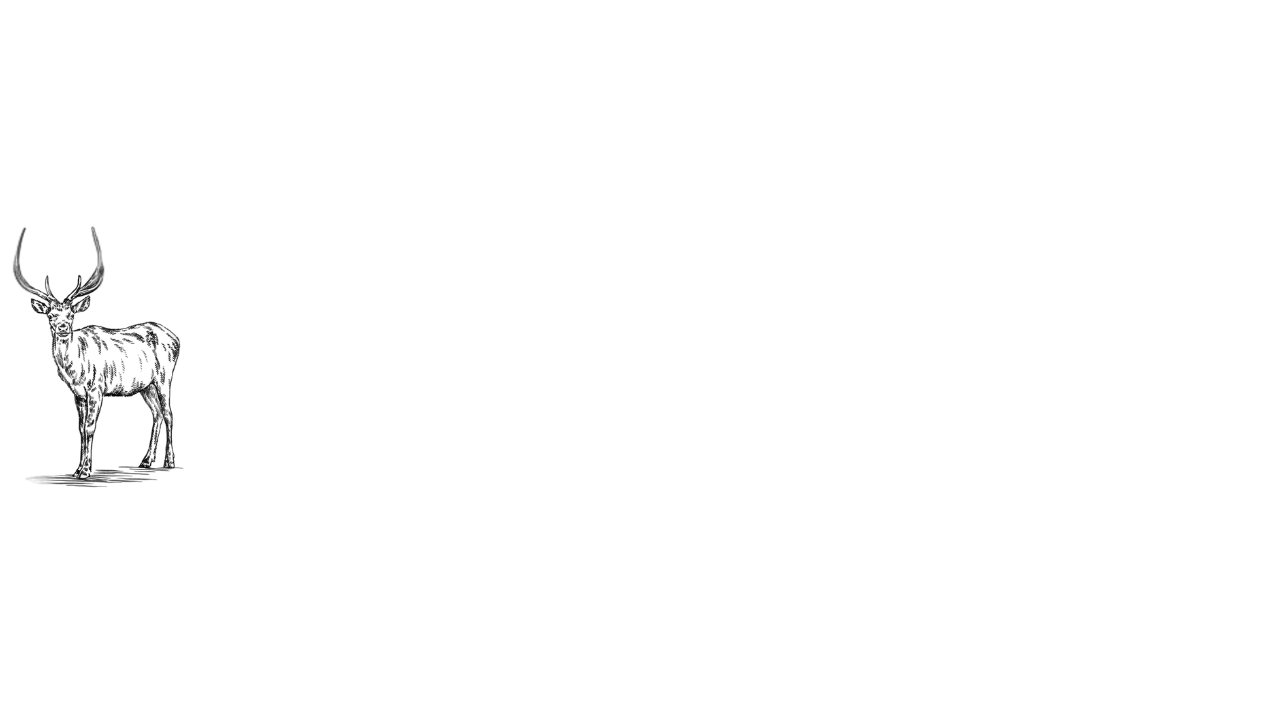【山菜】ヨモギの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
ヨモギは繁殖力が旺盛で、空き地や道端など、身近な場所でも見かけられます。
夏になる頃には成長して、草丈が100cm以上にもなります。
秋には目立ちませんが、小さな花が穂になって咲きます。
この記事では、そんなヨモギの生態や特徴・食べ方などについてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読めば、ヨモギのことはほとんど理解できますよ。
ヨモギの生態・特徴
ヨモギの生態
本州、四国、九州に生息する平地から山地までの日当たりの良い草地、土手、荒地などに生える多年草です。
地下茎を長く伸ばして繁殖します。
2〜3月ごろに細かい綿毛に覆われた根出葉を出し、裏に綿毛を密生させた葉をつけます。
ヨモギ類には、本種の他「オオヨモギ(ヤマヨモギ、エゾヨモギ)」「ニシヨモギ」「ヒトツバヨモギ」「オトコヨモギ」「カワラヨモギ」「リュウキュウヨモギ」「ユキヨモギ」「シロヨモギ」など、多くの種類があり、いずれも本種と同じように利用できます。
ヨモギの特徴
形状
根茎から長いふく枝を出して殖え、60〜150cmほどの大きさになります。
葉
長さ6〜12cmほどで、羽状に中〜深裂し、裏面と若芽全体に白色の綿毛が密生します。
この白い綿毛だけを集めて乾燥させたものが、もぐさです。
花期
9〜10月ごろ、葉先に円錐花序を出し、淡緑色の小さい花をつけます。
その他
葉や茎をちぎると、キク科特有の強い芳香があります。
ヨモギの時期・採集
街の空き地や河原、畑などどこでも生える多年草なので、群生していることが多く、ラクに最終できます。
葉の裏面と若芽全体に白い毛が密生する柔らかな茎先か若葉(5cmほど)を摘み取ります。
2〜3月に若芽を、6月ごろまでは茎先の柔らかい葉を採取します。

昔から若葉を摘んで餅につき入れたことからモチグサと呼ばれ、今でも春になるとヨモギ摘みにをする人の姿が見られます。
ヨモギの下ごしらえ・食べ方
葉は塩ひとつまみを加えた熱湯で10分ほど茹でて、冷水にとって20分さらします。

多く収穫した時には、下ごしらえしたものを冷凍保存します。
春菊に似た香味が楽しめます。
下ごしらえした若い葉を胡麻和えや味噌和えにするほか、細かく刻んだものを餅につき込んで草餅にします。

若芽や茎先にある葉は天ぷらにすると香味の良い一品になります。塩を軽くつけて食べるとヨモギの味が引き立ちます。
ヨモギの薬用・効果
6〜8月に葉を採取して、陰干ししたものが艾葉(がいよう)です。
これを臼で細かくつき砕いて、ふるいにかけて葉肉を除き、葉裏の綿毛だけにしたものが、お灸に用いるもぐさです。
葉の綿毛をお灸に用いる他に、葉を天日乾燥させて、腹痛、解熱などに煎じて服用します。
8〜9月に茎と葉を刈り取り、3〜4cmに刻んで、陰干しし、これを袋に入れて浴湯料にします。
あせも、肩こり、腰痛、神経痛の痛みを和らげてくれ、冷え性にも効果があります。

また、切り傷、虫刺されなどに生の葉の汁を塗ると良いです。
おわりに
この記事では、ヨモギの生態・特徴・食べ方についてまとめました。
下記では、他にも山菜について一覧にしてまとめていますので、こちらもぜひ参考にしてください。