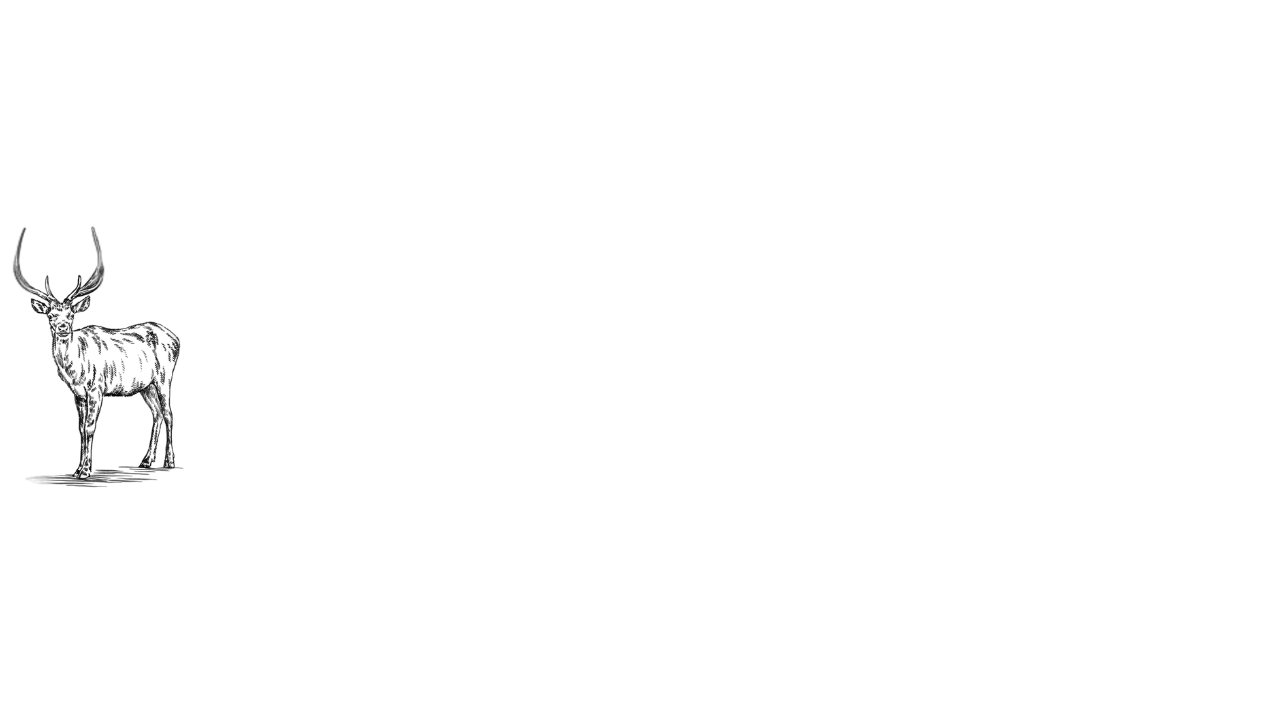【山菜】アザミの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
アザミには多くの種類があり、いずれも葉や茎に鋭いトゲがあります。
どの種類も山菜として新芽、茎、根が利用できます。
この記事では、そんなアザミの生態や特徴・食べ方などについてまとめましたのでぜひ参考にしてください。

この記事を読めば、しっかりとアザミのことを理解できるはず。
アザミの生態・特徴
アザミの生態
新緑を背景に紅紫色の花を咲かせ、夏の野山を彩るアザミは、日本に約60種類ほど自生しています。
しかし、品種によっては限られた地方にだけ生育しているものは、自然交雑種も多くあり、品種の特定は困難です。

アザミは花が美しいことから園芸品種に改良され、テラオカアザミなどの品種があります。
ノアザミは各地に分布しています。北海道のエゾアザミ、東北から本州中部に生えるナンブアザミ、関東から中部のトネアザミ、近畿から中国地方のヨシノアザミ、九州にはツクシアザミがあります。
山形県の西川町では、ノアザミのほか特に美味しいとされているものをヤチアザミ、山菜共和国で村おこしをしている新潟県の魚沼市大白川では茎の詰まったものをマイクロアザミ、フキのように空洞になっているものをブートアザミと呼んで、食用にしています。

ごく一般的に見られるノアザミは黒ずんで見た目はいまひとつかもしれませんが、クセはなくまろやかな味が特徴です。
アザミの特徴
どれも葉は複雑に裂け、縁に鋭いトゲがあります。
夏から秋にかけて筒状の小花が集まった4〜5cmの紅紫色の頭花をつけます。

一般的には紅紫色ですが、たまに白色もあります。江戸時代から園芸化され、黄色の花もあったといわれています。
アザミの時期・採取
4〜5月に若い茎や新芽を採取します。
トゲでケガをしないように、手袋を着用して採りましょう。
新芽のトゲは火を通すと柔らかくなり、食べる時には気になりません。

新芽は開いたばかりの頃のものを、茎は長さ20cm程度の若いものを採りましょう。
アザミの下ごしらえ・食べ方
皮をむき、ゆでて水にさらします。
苦味が気になるときは十分に水にさらしましょう。

下記では、アザミの下ごしらえについて画像付きで詳しくまとめていますのでこちらもぜひ参考にしてください。

塩漬けで保存できます。

漬物でお馴染みの「ヤマゴボウ」は多くの場合、モリアザミの根が利用されています。
茎はフキのように煮たり、油炒め、佃煮などに用います。
若芽は水洗い後に天ぷらや汁の実に使うと良いでしょう。
下ごしらえあり
和物(新芽、茎)
下ごしらえなし
天ぷら(新芽、茎)、佃煮(茎)、味噌漬け、醤油漬け(根)
アザミの薬用・効果
4〜5月にノアザミの全草を採取します。
生の茎葉を煎じた液は利尿に効果的といわれていますが、これは定かではありません。
また、煎じた液を湿疹の幹部に塗ると効果があるといわれています。
根を日干ししたものが生薬の大薊(たいけい)で利尿に、1日量10gをコップ3杯の水で半量になるまで煎じて、3回に分けて食前か食間に服用します。