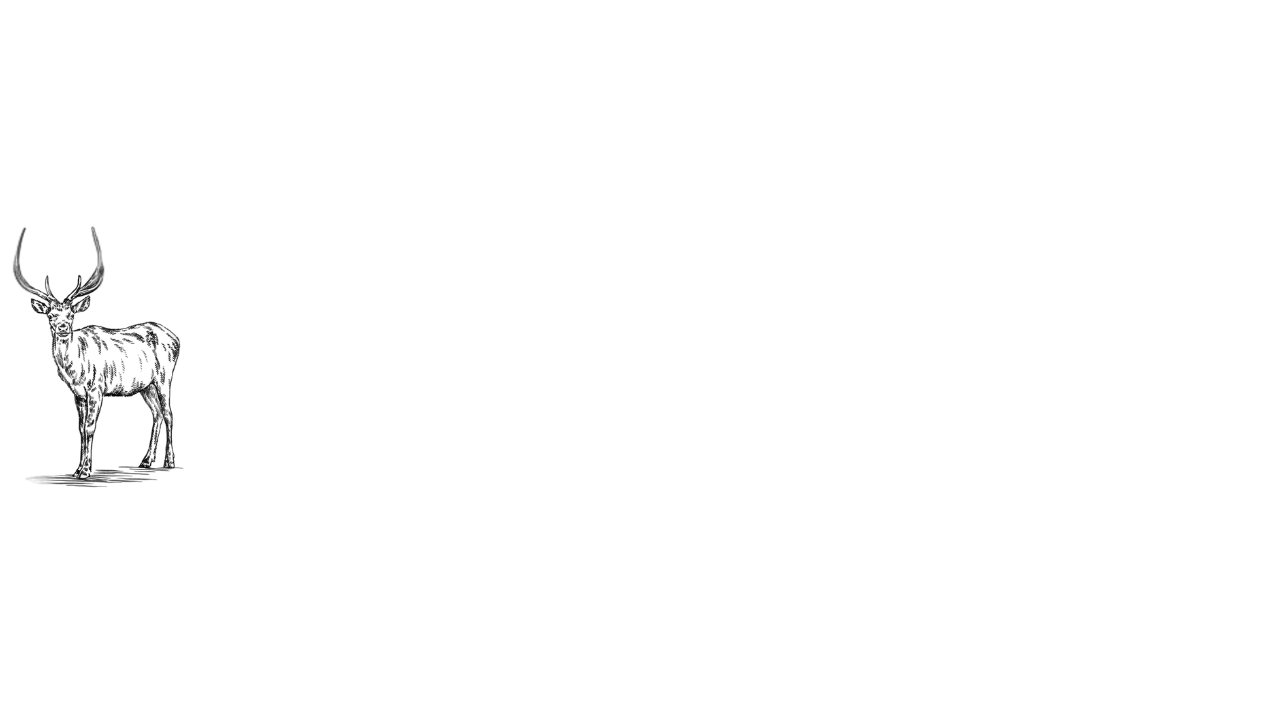【山菜】ゼンマイの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
最近水煮にされたゼンマイがスーパーマーケットの店頭に並ぶほどで、最もポピュラーな山菜の一つです。
ゼンマイの新芽は白色の綿毛で覆われていて、5本程度まとまって生えます。
この記事では、そんなゼンマイの生態や特徴・食べ方などについて詳しくまとめましたのでぜひ参考にしてください。

この記事を読めば、あなたもゼンマイマスター!!
ゼンマイの生態・特徴
ゼンマイの生態
平地から高山までの湿った草地、湿原、谷ぎわ、林床などに生える多年性のシダ植物で日本全土に分布します。
一般に東北地方が名産地で、春に山村を訪れると、民家の庭先でゼンマイ干しをしている光景に出会います。
根茎で増える繁殖力旺盛ですが、最近は採取のしすぎか、東北地方の産地でも大きな群落は山奥にしかなくなったといいます。
根茎から出る葉は食用になる葉と胞子葉からなり、春になると褐色の綿帽子をかぶって発芽します。

地方によっては茎が青みがかかっているものをアオゼンマイ、褐色に近いものをアカゼンマイと呼んで区別し、前者の方が美味しいといいます。
ゼンマイの特徴
形状
春に地中の根茎から、綿毛におおわれた新芽を出します。
伸びるにつれて綿毛が脱落して葉を開き、50〜100cmくらいの大きさになります。
葉
同一の根茎から栄養葉と胞子葉を出しますが、一般的には栄養葉のみ食用にします。
栄養は6〜7対の小葉と先端の1枚とからなる2回羽状複葉で50〜100cmくらいの大きさになります。
花期
花はつけません。
その他
似たようなものに「ヤマドリゼンマイ」があり、本種と同ゆに栄養葉の新芽を食用にします。
ゼンマイの時期・採取
4月ごろが適期ですが、雪の多いところでは7月ごろまで採取可能です。
茎の先が巻いた若い芽を下の方からしごくようにして、柔らかい部分で折り取り、茎の部分を食用にします。

全体が綿毛に覆われて葉が内側に巻いている時が良いです。
ゼンマイの下ごしらえ・食べ方
アクが強いので、木灰や重曹を用いてアク抜きをします。

木灰の方が美味しく仕上がるといいます。
乾燥させると、風味よく保存することができるので、下ごしらえしたものを、水分がなくなるまで、何度もよくもみほぐしながら、天日干しにします。
乾燥したものは、たっぷりの水に入れて火にかけ、沸騰する直前でゆで汁を捨てます。
これを3回繰り返し、3度目の水が熱くなったところで火からおろし、1日放置するとふっくらした状態に戻ります。

アク抜きと乾燥の方法は下記にてさらに詳しくまとめていますのでぜひ参考にしてください。

生でアク抜きしたものは、炒め煮、煮付け、白あえ、くるみあえ、汁の実と幅広く利用できます。
独特の歯応えとまろやかな風味があり、太くて柔らかいものほど高級とされます。

醤油と酒、砂糖で薄く味付けした炒め煮は柔らかくて溶けるような舌触りです。
下ごしらえあり
煮物、炒め物、和物、辛子和えや胡麻和え、炒め煮
ゼンマイの薬用
7〜8月に地上部を採取し、日干しにします。
利尿や貧血に刻んだもの10gをコップ3杯の水で半量になるまで煎じて服用しましょう。
おわりに
この記事では、ゼンマイの生態や特徴・食べ方についてまとめました。
下記では、他にも様々な山菜について一覧にしてまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください。