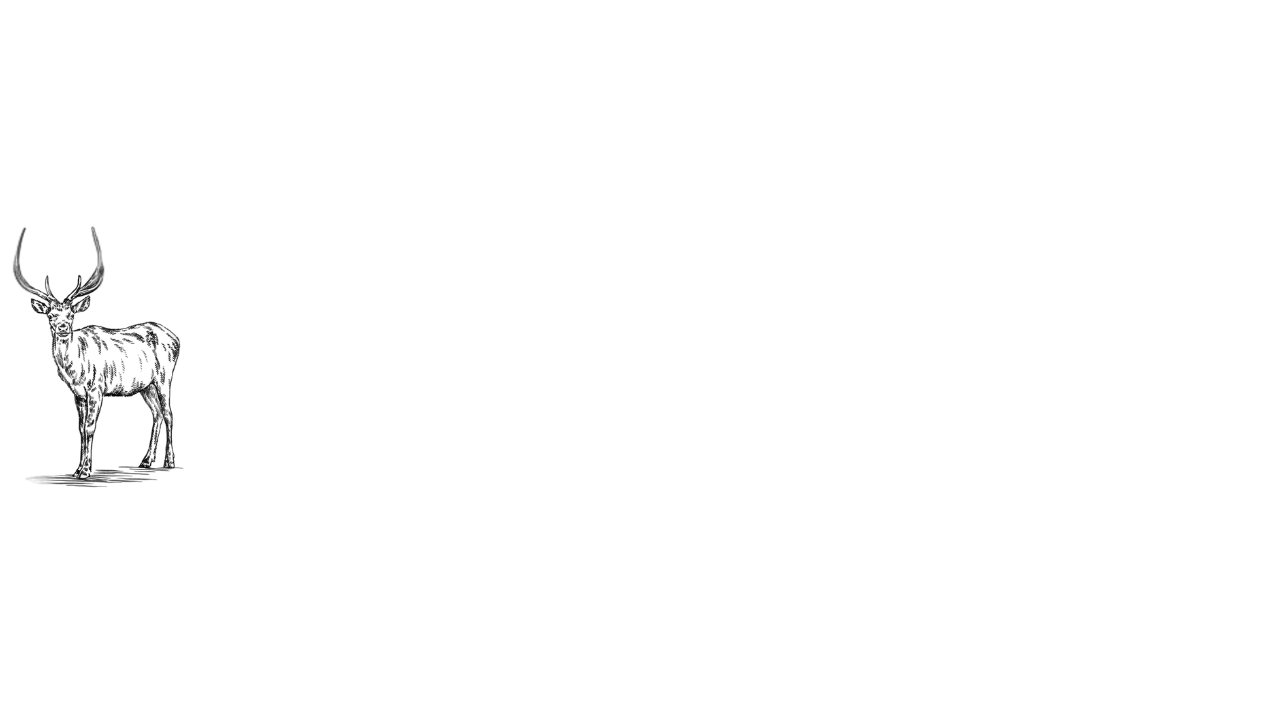【山菜】タラノメの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
万人がうまいと太鼓判を押すのが、昔から山菜の王と呼ばれるタラノメです。
タラノメはタラノキの枝の先端に伸びた新芽を食用にしたものです。
タラノメには油脂やタンパク質が豊富に含まれており、栄養価が高いといわれています。

近ごろ、コシアブラの方が美味しいという人もいますが、タラノメの人気は高く、温室で育てられたタラノメが春早々に都会の店頭に出回るほどです。
タラノメの生態・特徴
タラノメの生態
北海道、本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い荒地や林の縁、やぶぎわなどに生える落葉低木で、伐採地の斜面などにいち早く進入します。

東北地方の春山に入ると、積雪時にちょうど雪の上で芽吹いたところを、ウサギなどに食べられることがあります。
タラノメの特徴
形状
幹はあまり枝分かれせず直立し、大きなものでは幹の径12cmくらい、高さ4mほどにも伸びます。
全体に鋭く尖ったトゲにおおわれています。
葉
大型の2回羽状複葉で、互生します。
小葉は長さ5〜12cmくらいの卵形で、先端が尖り、緑には不揃いの荒いギザギザがあります。
花期
8〜9月ごろ、幹の先に大型の服総状花序をつけ、2mmくらいの小さな白色の5弁花を密につけます。
その他
全体に大型で、トゲがあまりないものを「メダラ」と呼び、同様に利用できます。
タラノメの時期・採取
4〜6月に若芽を摘み取ります。5〜15cmくらいの太くてころっとしたものが良品とされていますが、葉がやや伸びたくらいまでは、採取可能です。
手の届かない高い幹上につける場合が多いので、幹を折らずに曲げて、芽先だけを摘み取ります。

木全体や枝には鋭いトゲがあるので、採る時にはケガをしないように注意しましょう。
革手袋が必需品ですね。
枝先の芽を摘み取ると、やや下の方に二番芽がでますが、採取するのは二番芽までが限度です。
芽は一本の枝に数個しかつきませんので、全ての新芽を採ってしまうと、その株は枯れてしまいます。
三番芽まで摘むと、その枝が枯れてしまうので三番芽は残しましょう。。
また、新芽だけを見ると、毒草の「ウルシ」とよく似ていて間違う人が多いですが、ウルシには幹や枝にトゲがありません。
タラノメの下ごしらえ・食べ方
芽の基部についているはかまを取り除き、軽くゆでて水にさらします。。
新芽にはトゲがありますが、調理すると気にならなくなります。

塩漬けで保存できます。
何といっても美味しいのが、生のままで調理する天ぷらです。
特有の香りとほっこりした歯応えは最高です。
下ゆでしたものは、ごま味噌和え、クルミ和え、白和え、煮付け、卵とじなどにします。
また、酒のアテとしては焼き味噌と一緒に細かく刻んだ切り和えがオススメです、
下ごしらえあり
ゴマ味噌和え、クルミ和え
下ごしらえなし
天ぷらやフライ、汁の実、直火焼き
薬用としては、樹皮を天日乾燥し、健康整腸、糖尿病、神経痛などに煎じて服用します。