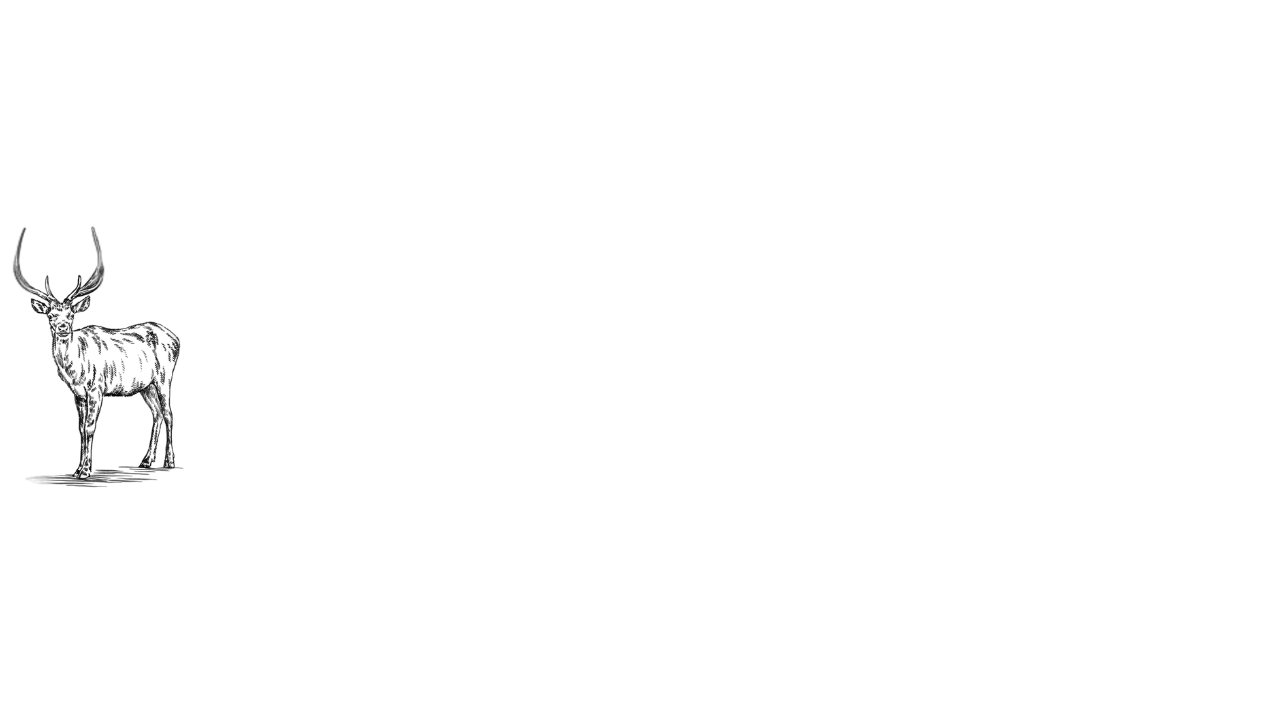【山菜】イタドリの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
子どもの頃、河原などで遊んでいてのどが乾くと、イタドリを折り取って皮をむき、酸っぱい味を楽しんだ経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
イタドリの生態・特徴
イタドリの生態
イタドリは北海道、本州、四国、九州など全国に分布する多年草です。
人家に近い河原や荒地、野山などに自生しています。
イタドリの特徴
形状
新芽は茎に節があり、早春にタケノコのような形をしています。
生長につれて、斜めに立ち上がって大型の葉を広げ、1mを超える高さになります。

寒い地域に多く見られるオオイタドリは3mほどになります。
葉
細めの茎に、長さ6〜15cmくらいの広卵形の大型の葉が互生します。
花期
雌雄異株です。7〜10月ごろ、各枝の節に白色〜淡紅色の小さな花を房状につけます。
その他
近縁に「ケイタドリ」「ハチジョウイタドリ」「オオイタドリ」があり、どれも同じように食べることができます。
イタドリの時期・採集
3〜5月に伸び出して間もない若い芽を採取しましょう。
タケノコ状に伸びた若茎を利用しますが、太くて、短いものを選び、基部からポキリと降りとるか、ナイフで切り取ると良いです。
イタドリの下ごしらえ・食べ方
アクは弱いので、生食もできますが、シュウ酸(尿路結石や下痢の原因となるもの)を含むので、食べ過ぎや続けて食べることは避けたほうが良いです。

イタドリの若芽は、のどが渇いた時などに、折取ってかじると、爽やかな酸味で口を潤してくれます。
皮をむいてからゆでて、水にさらしましょう。

塩漬けで保存できます。
下ごしらえしたものを酢の物、煮浸し、油炒めなどにすると、歯応えのある惣菜になります。
酸っぱいままのものを塩漬けにすると、強烈な酸味で、目が覚めるような逸品になります。
下ごしらえアリ
サラダ、マヨネーズ和えや納豆あえ、酢の物
下ごしらえなし
天ぷら
イタドリの薬用・効果
秋に根茎を掘り取り、水洗いして干したものが生薬の虎杖根(こじょうこん)です。
一日量8gをコップ三杯の水で半量に煎じ、食間3回に分けて服用すると、便秘、月経不順に効果的といわれています。

イタドリの名前は、擦り傷に若芽をもんで柔らかくしたものをつけると痛みがやわらぐ「いたみとり」に由来するという説がありますが、成分を見て、この説は誤解といえそうです。