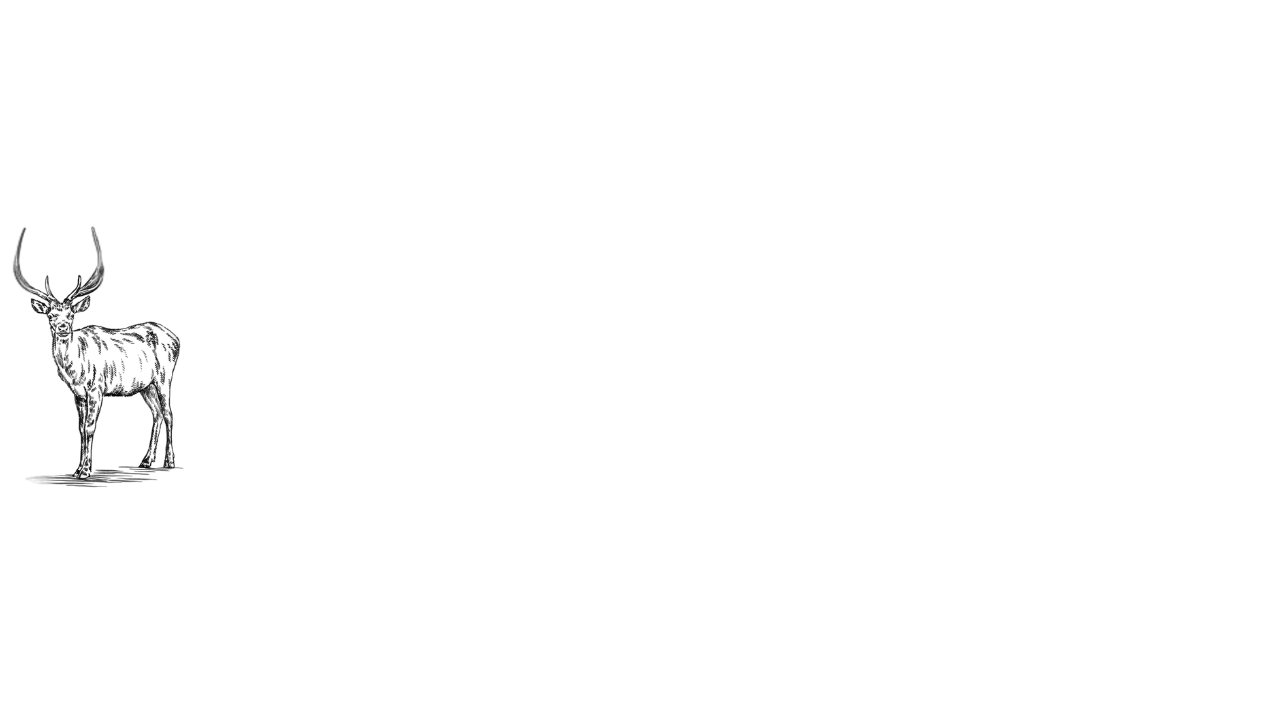【山菜】 サンショウの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
サンショウはポピュラーな山菜の一つです。
この記事では、そんなサンショウの生態や特徴・食べ方などについてまとめましたのでぜひ参考にしてください。

この記事を読めば、サンショウについて深く理解できますよ〜
サンショウの生態・特徴
サンショウの生態
林の縁や渓流ぎわに多く生える落葉性低木で、湿り気のある場所を好みます。
北海道、本州、四国、九州に分布します。
葉や果実には、ジペンテン、シトロネラール、サンショールなどの精油を含んでいるので、生の葉をもむと良い香りがし、口に含むと辛みがあります。

このため昔から料理の薬味や生薬として利用されてきました。
似た仲間には、トゲのないヤマサクラサンショウ、サンショウのトゲが対生なので対して互生しているイヌザンショウがあります。
食用にできますが、イヌザンショウは香りが良くないので食べません。
サンショウの特徴
形状
中心となる幹から横に枝をつけ、1〜5mくらいの高さになります。
若い枝には、葉のわきに一対のトゲを対生させ、古木になると樹皮がコルク化します。
葉
9〜19枚の小葉からなる奇数羽状複葉で互生します。
小葉は長さ15〜35mmくらいの卵状長楕円形で、先端が浅く裂け、緑には鋭いギザギザがあります。
花期
4〜5月ごろ、枝先の複総状花序に緑黄色の小さな5弁花をたくさんつけます。
その他
花の後、5mmくらいの球果を結び、秋に紅く熟して裂開し、光沢のある黒色の種子があらわれます。

雌雄異株なので、雄株には実がなりません。
サンショウの時期・採取
4〜5月ごろに若芽や花穂を、5〜6月に若い果実を採取します。
片方の手で枝先をつまみ持ち、トゲに注意しながら残りの手の指先で摘み取ります。
サンショウの下ごしらえ・食べ方
春には新芽、夏には若い実、秋には熟した実が利用できます。
若い実は、中のタネが白色で、柔らかいものを利用します。
アク抜きすることなく、生のまま使用できます。
若芽の佃煮は珍味です。
また、すりつぶして味噌と混ぜたサンショウ味噌は、豆腐やサトイモの田楽に欠かせませんし、鮎のサンショウ味噌焼きも優れた一品です。
若い果実は昆布などと一緒に醤油で煮付けると美味しい佃煮になります。
佃煮(新芽)、山椒味噌、醤油漬け、熟した実の皮だけを天日干し、すりつぶして粉サンショウに
サンショウの薬用・効果
8月下旬ごろに、黄ばんできた果実を採取します。
これを陰干しして果皮のみを集めたものが生薬の山椒で、漢方薬の材料になります。
民間では、胃痛の時に山椒の粉末を小さじ半分ほど飲むと効果的といわれています。

他には、虫刺されに生の葉のもみ汁を塗布します。
おわりに
この記事では、サンショウの生態・採集・食べ方などについてまとめました。
下記では、他にも様々な山菜を一覧にしてまとめていますので、こちらもぜひ参考にしてください。