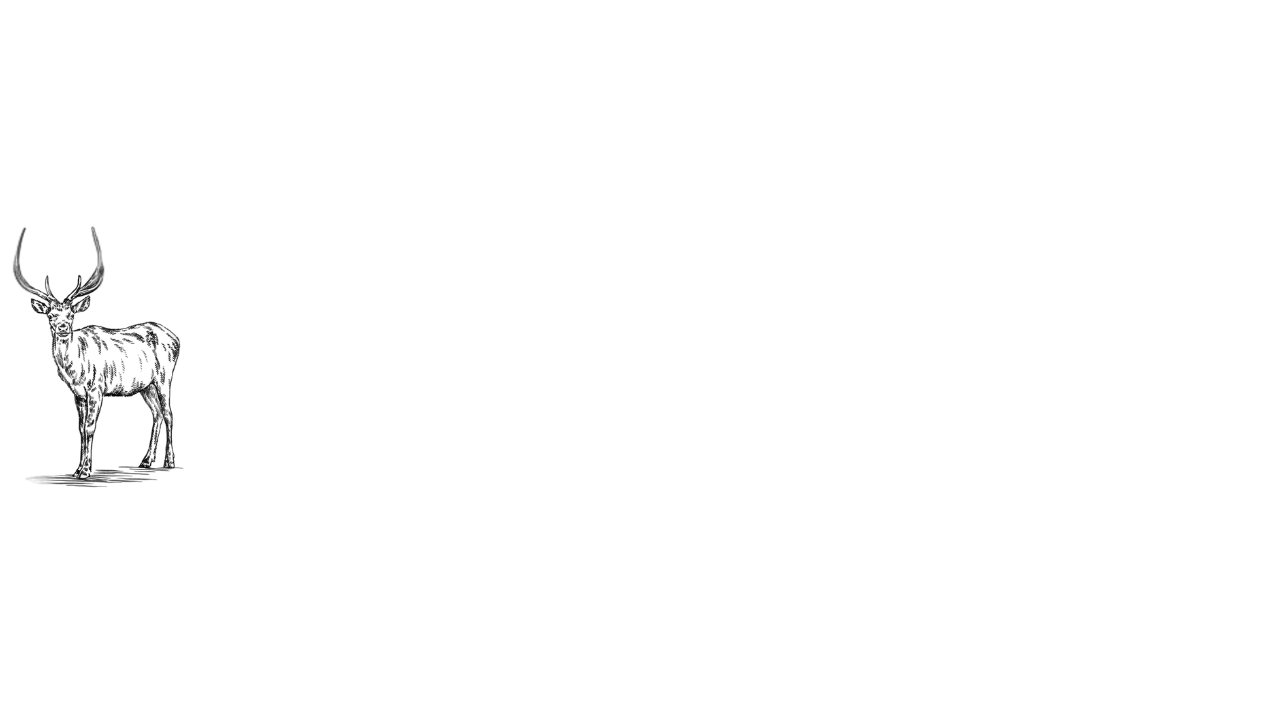【山菜】 ワサビの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
ワサビは日本の代表的な香辛植物で、刺身に欠かせません。
香辛料というと香りと辛みだけのように思えますが、ワサビは不思議なもので、ツンとした鼻にくる辛味のあとに残る甘さがなんとも魅力的で、良いワサビに出合うと刺身が一段と美味しくなります。
この記事では、そんなワサビの生態や特徴・食べ方などについてまとめていますのでぜひ参考にしてください。

この記事を読めばワサビのことをしっかりと理解することができますよ〜
ワサビの生態・特徴
ワサビの生態
ワサビはキレイな水の流れのそばに生えています。
山地の谷川の浅瀬や流水ぎわ、水が滴り落ちる岩壁などに生える多年草で、北海道、本州、四国、九州に分布します。
栽培されていることが多いので、採取する際には場所を確認することが大切です。
静岡県や長野県で盛んに栽培されており、山菜というよりは、ワサビ田で栽培される栽培品というイメージが強いのですが、ワサビはれっきとした山菜の一つです。

しかも天然の方が格段に香りが良いといわれるので、ぜひ天然のワサビを手に入れてみたいものです。
ワサビの特徴
形状
春早くに長い柄のある根性葉を束生し、程なく花茎を伸ばして20〜50cmくらいの高さになります。
葉
根性葉は長い柄があり、長さ、幅とも8〜10cmくらいの円心形で、縁には浅い波状のギザギザがあります。
表面はシワがよった感じがして光沢があります。
花期
4〜5月ごろ、花茎の先に総状花序を出し、長さ8〜9mmくらいの白い十字形花を球状につけます。
その他
花の後、長さ15〜17mmくらいの数珠状にくびれた長角果を結びます。
ワサビの時期・採集
開花期から結実期(4〜7月ごろ)にかけての根茎は、辛味も風味も乏しいため、この時期は地上部だけを摘み取り、根茎は8月以降に掘り取るのが良いです。
同属の「ユリワサビ(食用)」は全体的に小型で、葉柄の基部が黒紫色に膨らんでユリ根に似ます。
根茎は1〜2mmと細く、根性葉は2〜5cmの腎円系で葉と茎は食用できます。
自生しているワサビの根は小さく、数も年々減っていることから、山菜としては根はとらず、主に葉や花を利用します。

全体的に小型で、山中の湿気のある場所に生えるユリワサビも同じように利用できます。
ワサビの下ごしらえ・食べ方
アクはなく、塩ひとつまみ加えた熱湯にくぐらせ、冷水にとって5分ほどさらします。
おひたしの場合は、一口大に刻んで塩でもみ、上からまんべんなく熱湯をかけたらすぐ冷水にとって熱をとります。
水気をしぼって容器に移し、冷蔵庫に一晩おいてから食べると良いです。

ワサビの香りと辛味は細胞が壊れた時に効果が発揮されるので、出来るだけ細胞をすり潰すように目が細かく詰んだおろし金やサメ皮を張ったおろし金を用いると風味が増します。
下ごしらえアリ
おひたしやサラダ
下ごしらえナシ
塩をまぶして軽くもみ、熱湯をかけてふたをしてしばらく蒸した後、水気を絞って鰹節と醤油をかける。
ワサビの薬用・効果
根茎などの辛味成分には、食欲増進、健胃効果があります。
民間薬としては、リウマチや神経痛の痛みに、すりおろした根茎をガーゼで包んで、1回約20分患部に当てると、一時的に痛みが和らぐといいます。
おわりに
この記事では、ワサビの生態や特徴・食べ方などについてまとめました。
下記では、他にも様々な山菜について一覧にしてまとめていますのでぜひこちらも参考にしてください。