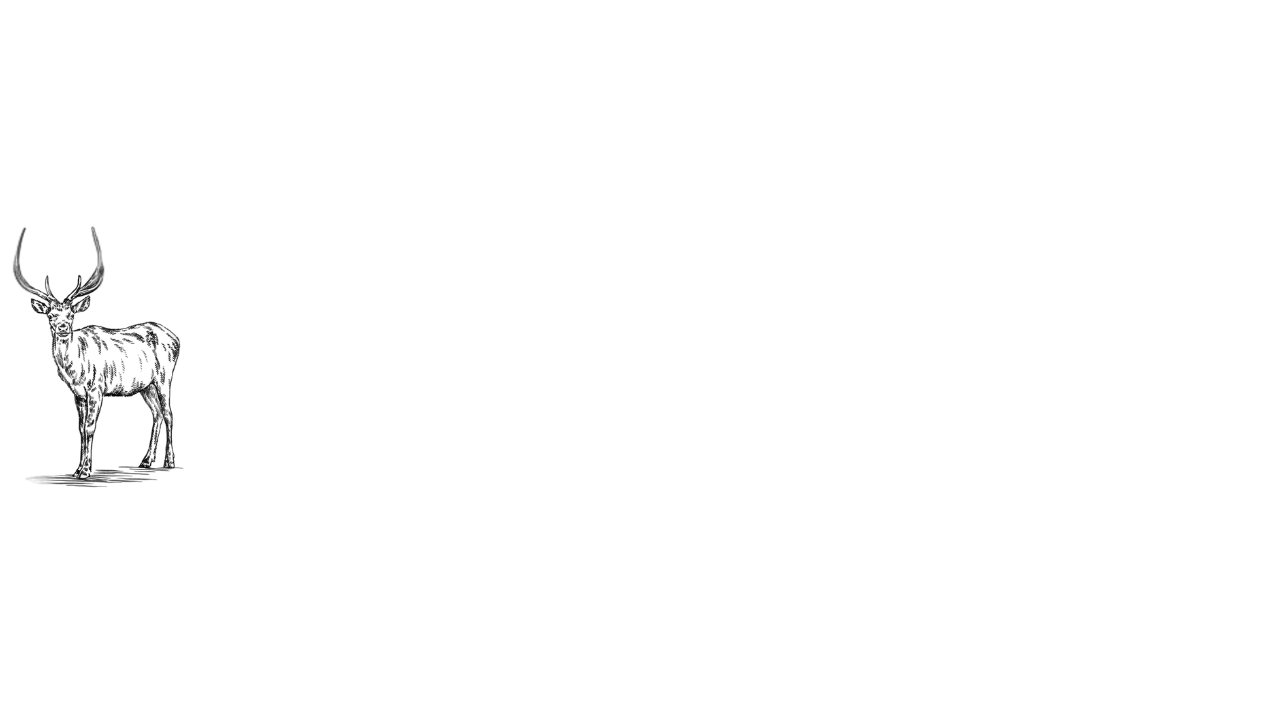【山菜】 ヤマノイモ(ムカゴ)の特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
ヤマノイモは自然薯とも呼ばれていて昔から「自然薯を食べると精がつく」といわれるほど、滋養強壮効果の優れた山菜です。
漢方薬の世界でも山薬(さんやく)と呼んで滋養強壮に使っています。
また、ムカゴは葉のつけ根につく小さなイモです。
根と同じように粘りと風味があります。
ヤマノイモの生態と特徴
ヤマノイモの生態
本州、四国、九州、沖縄に分布し、平地から山地までのやぶきわや林の縁に生えるつる性多年草で、比較的日当たりの良い場所を好みます。
ヤマノイモの特徴
形状
つる茎を左巻きに他物にからめて伸び、5mほどの長さまで伸びます。
葉
長さ5〜10cmくらいの三角状狭卵形で、先端が鋭く尖り、基部は湾入します。
長めの柄があり、茎に対生するのが大きな特徴です。
花期
雌雄異株で7〜8月ごろ、葉のつけ根から2〜5個の穂状花序を伸ばし、白色の小さい花をたくさんつけますが、雄花の花穂は上向きにたち、雌花の花穂は下に垂れます。
その他
9〜10月ごろ、葉のつけ根に1cmくらいの球形のムカゴ(珠芽【しゅが】)をつけます。
ヤマノイモ(ムカゴ)の時期と採取
秋にムカゴを、秋から冬にイモを掘り取ります。
根は地中深くにほぼ真っ直ぐ伸び、折れやすいので、掘り上げるのには大変な作業になります。
塊根は斜面から生えているつるを探して掘るのがラクです。
大小のスコップ、マイナスドライバーなどがあると便利です。
若葉は柔らかな芽先を摘みます。
よく似ている野草に食べるのには適さない「オニドコロ(トコロ)」がありますが、オニドコロは葉が円心形で互生します。
また、根茎は横に伸びてかたく、苦味が強いです。
ヤマノイモの下ごしらえと食べ方
塩ひとつ加えた熱湯で5分ほどゆでて、冷水にとって7〜8分ほどさらします。
ムカゴはご飯に炊き込んだり、油炒め、唐揚げにします。
イモはとろろ汁のほか、すりおろしたイモを海苔で巻いて油で揚げた磯部巻き、粗い千切りにしてサラダ、天ぷらにします。
下ごしらえアリ
すりおろしてだし汁をとってとろろ汁に(根)
下ごしらえなし
唐揚げ(ムカゴ)、炊き込みご飯(ムカゴ)、塩茹でしてから和え物に(ムカゴ)
ヤマノイモの薬用と効果
11月ごろにイモを掘って外皮を除き、日干しにしたのが生薬の山薬(さんやく)です。
漢方で滋養強壮の目的で処分されます。
民間薬としては、寝汗や夜尿症に、生のイモをアルミホイルで包み焼きにしたものを、塩につけて毎日食べると効果があるといわれています。
おわりに
この記事ではヤマノイモの生態や特徴・食べ方についてまとめました。
下記では他にも様々な山菜についてまとめていますのでぜひこちらも参考にしてください。