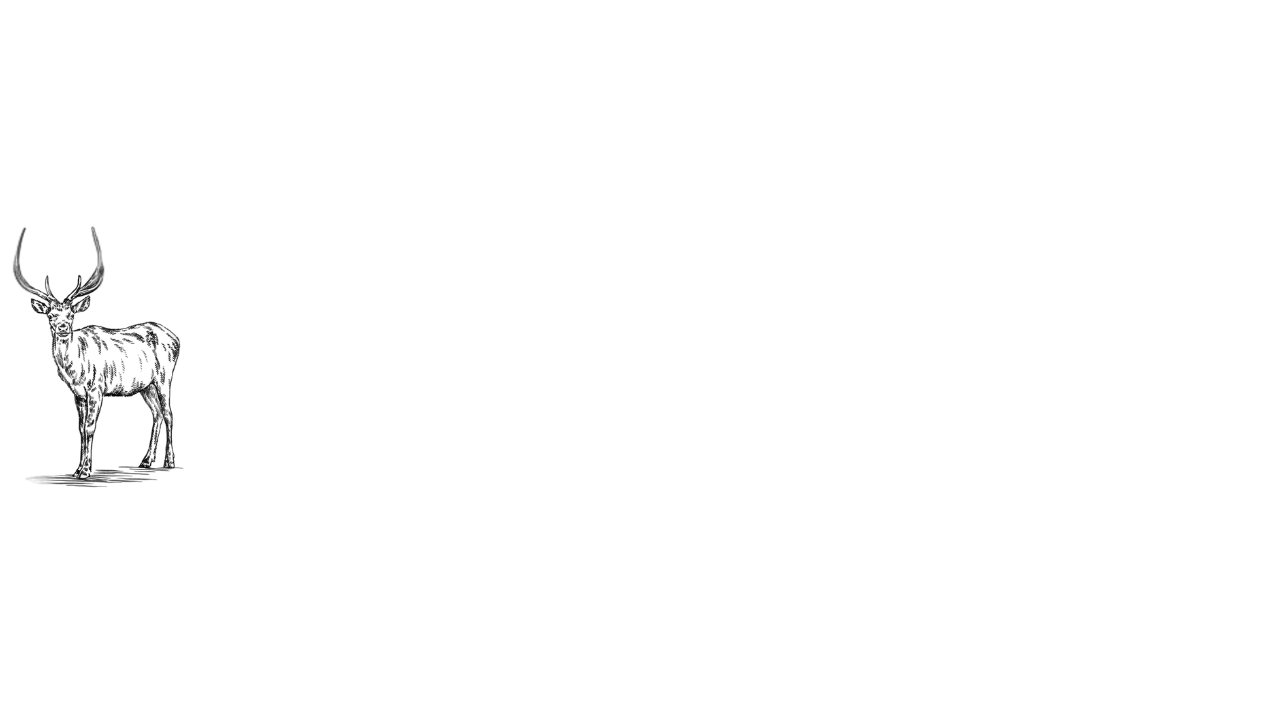【徹底解説】身近にある毒草【20選】
山を散策し、山菜を探していると山菜によく似た毒草を見つけることがあります。
この記事では、身近にある毒草を厳選して紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
トリカブト
猛毒を持つ植物として有名です。
若芽の頃は、山菜のニリンソウに似ています。
全国に分布し、ニリンソウと同じような場所に生えるので、注意して見分ける必要があります。
トリカブトは全体的に毒成分を有し、地下部には長さ3cmの逆三角形をした塊根(烏頭と呼ぶ)をもち、秋にはやや小型の子根(ぶし)をつけます。
生長すると50cm〜1mになり、3〜5つに深く切れ込んだ掌状の葉をつけます。
夏から秋に茎の先端に、舞楽の鳥兜に似た青紫色の花をつけます。
似た仲間にヤマトリカブト、オクトリカブトがあり、いずれも猛毒があります。
毒の成分はアルカイドで、全草、特に塊根に多く含まれています。
誤食すると呼吸困難、心臓麻痺を引き起こして死に至ります。
ニリンソウとの見分け方は塊根のあるなしでできますが、採集時期はニリンソウの花を確認するのが一番です。
コバケイソウ
ギボウシの若芽と間違って誤食しやすい毒草です。
ベラトラミンなどの有毒成分を含み、血圧が下降してめまいや脱力感を生じ、呼吸麻痺を起こして死に至ることがあります。
コバケイソウは北海道、本州、四国、九州に分布し、ギボウシと同じ山地のやや湿ったところに自生しています。
生長すると60cm〜1mになり、幅の広い楕円形の葉をつけ、初夏に花を咲かせます。
ギボウシと異なり、苦い味がしたらコバケイソウです。
アセビ
ツツジ科の常緑樹で、鈴のような可愛い花を咲かせることから庭木や生垣に使われます。
同じ仲間にオキナワアセビ、タイワンアセビがあります。
植物全体に強い毒成分を含み、誤食すると嘔吐、下痢を引き起こします。
イケマ
ガガイモ科の蔓性の多年性で、茎や地下茎に毒成分を持っているために注意が必要です。
茎を折ると白い乳液が出ます。
有毒成分のシナンコトキシンを含み、誤食するとよだれが出て、嘔吐し、けいれんを引き起こします。
ウマノアシガタ
キンボウゲの名で親しまれている多年草で、日当たりの良い野原や山野に自生しています。
初夏に光沢のある黄色の5弁花をつけます。
全草にラヌンクリンなどの毒成分を含み、水ぶくれなどの皮膚炎を起こすほか、誤食すると嘔吐したり、胃腸に炎症を起こすことがあります。
ウスバサイシン
ウマノスズクサ科の多年草で、本州、四国、九州北部に分布しています。
山地のやや湿った林床に自生する植物で、その根および根茎を乾燥させたものは細辛(さいしん)と呼ばれ、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)や小青竜湯などの漢方処方に配合されています。
しかし、その地上部には、アリストロキア酸という有毒成分を含有し、腎障害を引き起こす可能性がありますので、食べてはいけません。
キツネノカミソリ
ヒガンバナ科の多年草で、全国の野山に自生しています。
8〜9月に40cmほどの花茎を伸ばしてオレンジ色の六弁花を咲かせますが、花は彼岸花のように反りかえりません。
全草にアルカロイドのリコリンを含み、誤食すると嘔吐、下痢、場合によってはけいれんを起こして死に至ることもあります。
キツネノボタン
セリに似ているので採取時は注意が必要です。
全国に分布し、日当たりがよくやや湿った水辺などを好んで生える越年草です。
20〜80cmで、春から秋まで花径1cmぐらいの黄色い花を咲かせ、花後に金平糖のような果実を結びます。
全草に有毒成分プロトアネモニンを含み、皮膚炎になったり、誤食すると胃腸の炎症を引き起こします。
クサノオウ
山野、草原、市街地の空き地などに生えるケシ科の越年草です。
高さは40〜80cmで、切れ込みのある葉を互生し、全体に白っぽい感じです。
初夏から夏に黄色の4弁花をつけます。
茎を折ると黄色の乳液が出ます。
全草に毒成分のケリドニンなどを含み、誤食するとけいれん、呼吸麻痺などを引き起こすことがあります。
スズラン
芳香を放ち、花が可愛らしいことから、園芸植物として有名です。
園芸店で売られているもののほとんどはドイツスズランです。
日本の自生種は小型で、花つきも少ないことから、山野草として親しまれています。
全草に、特に根茎にコンバラトキシン、コンバラサイトなどの毒成分を含み、誤食すると、嘔吐、頭痛、時に心臓発作を起こすことがあります。