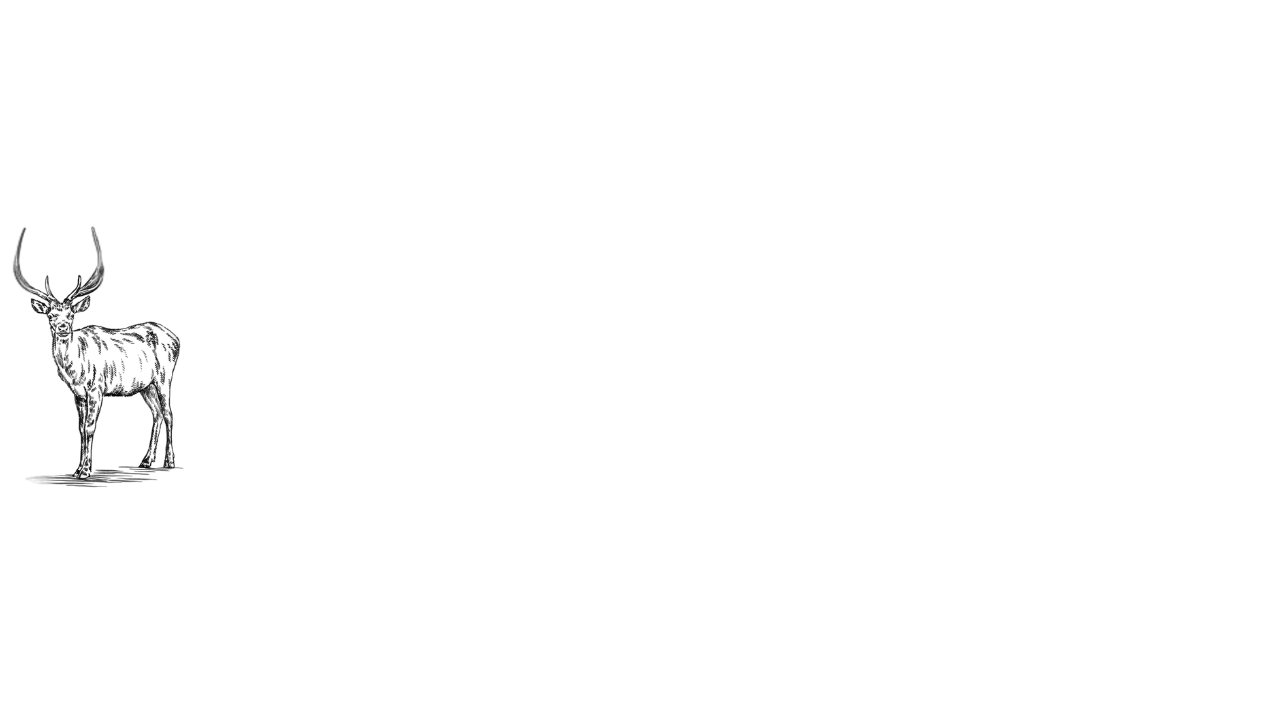【山菜】フキノトウの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
フキノトウはフキの花のことです。
フキはまず花が咲き、その後に葉が伸びます。
葉は葉茎を伸ばしながら成長し、やがて大きな葉を広げます。
綿毛のついたタネができ始めると、花茎が成長します。
花茎も葉茎と同じように利用できます。

沢沿いなど湿気の多い場所では、柔らかく質の良いものが育ちます。
この記事では、そんなフキノトウの特徴や収穫時期・食べ方などをまとめました。

この記事を読めば、フキノトウについてしっかりと理解できますよ。
フキノトウの生態・特徴
フキノトウの生態
本州、四国、九州、沖縄の平地から山地までの荒地、野原、土手、河原などに広く生える多年草で、湿り気のある場所を好みます。
春早くに顔を出す「フキノトウ」は花茎(かけい)にあたり、葉は花の後に出ます。
フキノトウの特徴
形状
フキノトウと呼ばれる花茎は、うすい鱗片葉に包まれた、球形で、花を咲かせた後に30〜40cmぐらいの高さになります。
そこからさらに、地中の茎から葉を伸ばし1mほどの高さになります。
葉
長い葉柄の先に、15〜30cm ほどの大型のひし形で、緑に粗いギザギザがある葉を水平に開きます。
花期
雌雄異株で、2〜6月ごろ、花茎の先に散房状に花をつけます。
雌株の花は白色、雄株の花は黄色です。
その他
フキの亜種にアキタブキがあります。
秋田県以北から北海道にかけて自生しており、葉柄には人の背丈以上で葉も巨大です。

にわか雨の際には、傘の代わりになるほど大きいです。
アキタブキが覆いかぶさるように茂る、うっそうとした「フキの森」には、コロボックルと呼ばれる小人たちが住んでいたというアイヌ伝説が残されています。

栽培の歴史は古く、関西以西でも多く栽培されている「愛知早生フキ」、京都や奈良などで栽培されている「水フキ」などが有名です。
フキノトウの時期・採集
食材としては、2〜3月ごろに生じるフキノトウのつぼみから始まって、花茎を伸ばして頭部に花を咲かせるフキノトウ、春から夏にかけて30〜40cmの葉柄を伸ばして大きな葉をつけるフキなど、早春から夏まで採取できます。
特に、北国では4〜5月に雪解けを待ちかねたように顔を出すフキノトウは、春を告げる味覚として、新鮮な香りとほろ苦さがが珍重され、箸休めの一品として食べられています。
フキノトウの生育場所は湿気のある山道や草地、田んぼのあぜなどです。
フキノトウは、鱗片葉が開く前のものを摘み取ります。

葉柄をとる場合は、5〜9月ごろの茎が30〜50cm成長したものを取りましょう。
フキノトウの下ごしらえ・食べ方
よく洗って、フキノトウ味噌や天ぷら、煮付けにして早春の香りを楽しみます。

天ぷらにする場合は、中のつぼみを取り除いて揚げると、苦味が抑えられます。
天ぷらにする以外は、塩をひとつまみ入れて熱湯で10分ほど茹で、水に30分ほどさらしてアク抜きをします。

フキノトウを採取したら、苦味が強くならないように、できるだけ早く調理するのがコツです。
フキノトウの味噌を作る場合は、刻んだ生のフキノトウと味噌、酒を合わせて火にかけ、煮すぎると香りが抜けるので、注意しながら練り上げます。

ほろ苦さ、新鮮な香り、味噌の味が口の中で絡み合い、酒のすすむアテになります。
葉柄は夏に採取します。アク抜きをして水にさらしながら皮をむき、おひたしや煮物、粕漬けなどにします。
また、フキノトウは文字通りとうが立ってからでも、花茎を摘み取って軽くゆでてアク抜きをして、フキ同様煮物にできます。

その他にも甘酢漬けや佃煮などがありますよ。
フキノトウの薬用・効果
咳止めや痰切りに効果があるとされています。
葉やつぼみを採取して陰干しし、1日10〜15gをコップ3杯の水で半量になるまで煎じて、食前3回に分けて服用します。
おわりに
この記事では、フキノトウの生態や特徴、食べ方などについてまとめました。
下記では、他にも山で採れる山菜についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。