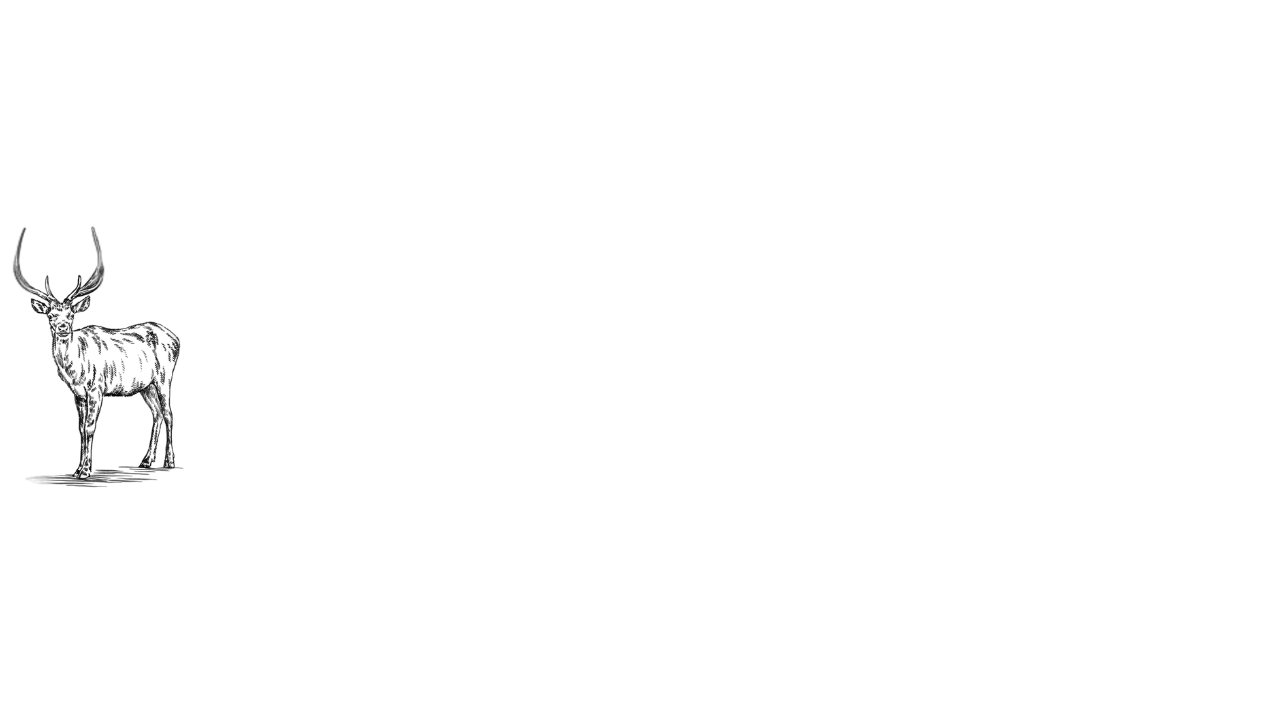【山菜】ワラビの特徴は?時期と食べ方【徹底解説】
ワラビは誰でも知っているポピュラーな山菜で、クセのない香りと特有のぬめりで広く親しまれています。
日当たりの草原などに生える、シダ植物の新芽で、葉が開く前の新芽の先端は、握りこぶしのような形をしています。
人気の高い山菜で、シーズンになると店先にも並べられます。
この記事では、そんなワラビの生態・特徴・食べ方などについてまとめています。

この記事でを読めば、ワラビについてしっかりと理解することができますよ。
ワラビの生態・特徴
ワラビの生態
日本全土に分布する平地から山地までの日当たりの良い草地、土手、林の縁、伐採地などに生える多年生のシダ植物です。
場所によって生育状態が異なり、かやの下からいち早く芽を出したワラビは養分と日当たりが良いためか、太くてしなやかなものが多い。
ワラビの特徴
形状
良質のデンプンを含む肉質の根茎から、握りこぼし状の新芽を伸ばし、これが生長して葉になり、1.5mほどの大きさになります。
葉
2〜3回羽状複葉で、全形は卵状三角形になります・
裏面には軟毛があり、各小葉の裏面の縁に、胞子のう群が連続的につきます。
花期
花はつけません。
その他
根茎からデンプンをとって、精製してワラビ粉を作ることができます。
ワラビの時期・採集
4月ごろから北国では6月ごろまでが採集適期で、葉の先端がこぶし状に丸まった若芽を採集します。
群生することが多く、茎が太いものを選んで採ります。
若芽を下から上へしごいて、自然に次りとれるところから摘み取ります。
採ったワラビは手の温もりですぐにかたくなるので、切り口を下にして、カゴなどに入れます。

前年の枯れた葉を目印にして周囲を探します。毎年同じ場所に出るので成長した葉を見つけたら、場所を覚えておきましょう。
ワラビの下ごしらえ・食べ方
下ごしらえ
ワラビはアクが強いので丁寧にアク抜きをします。
ゆでると、柔らかくなって歯応えがなくなってしまうので、熱湯をかけてアク抜きをします。
ワラビを鍋に入れて布をかけて、その上に木灰(草木を焼いて作った灰)もしくは重曹(重炭酸ソーダの略で炭酸水素ナトリウムのこと)をまぶし、上から満遍なくひたひたになるまで熱湯を注ぎかけて30分おき、冷水にとって一晩さらします。
まぶす木灰の量は、ワラビの重量の10〜15%が目安です。


採取した直後なら、熱湯を注いで15分おき、冷水で30分さらす程度で良いです。
食べ方
おひたしにするとワラビ本来のぬめりと風味が味わえます。
白あえ、くるみあえ、からしあえ、マヨネーズあえなど、他の味とあえても美味しく食べられます。
また、煮付け、煮浸し、汁の実にしても素朴な風味と独特な歯応えを楽しめます。
このほか、根からはデンプンがとれます。

これを材料に作ったのが本当のわらび餅ですが、市販されているわらび餅の大半は、小麦粉から作っています。
ワラビの薬用・効果
あくに発がん性物質があるといわれて敬遠されたこともありましたが、実際は発がん性物質の影響が懸念されるには毎日大量に食べ続けることを仮定したものであることを踏まえれば、惣菜としてほどほどに食べる分には問題なさそうです。
おわりに
この記事では、ワラビの生態や特徴、採取・食べ方についてまとめました。
下記では、他にも山菜について一覧にしてまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください。